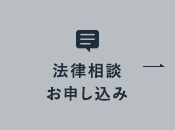2025/05/27 弁護士雑感
【弁護士雑感】カスタマーハラスメント(カスハラ)に企業はどう対応すべきか?法的観点と実務対応まとめ
1 はじめに
「お客様は神様」というのは正しいのでしょうか。この言葉は、製品を開発・製造する際またはサービスを提供する際に、顧客のことを第一に考え、製品やサービスをより良いモノにするためのスローガンのようなものです。
企業は、顧客からのクレームや苦情により、商品・サービスや接客態度・システムなどに対する不平・不満を拾い上げ、それらを神様のように取り扱い、対応・改善することで業務改善や新たな商品・サービス開発へ繋げます。
そのように、「お客様は神様」という言葉は、製品やサービスを”提供する側”が、自らに課すためのものでありますが、しばしば、そのことを誤解し自身がお客様であり、神様であるとの前提で過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける不当・悪質なクレーム(いわゆるカスタマーハラスメント)があります。こういったカスタマーハラスメントは業務に支障をきたすだけでなく様々な問題を生じさせるものであるため、企業として適切に対処する必要があります。
この記事では、カスタマーハラスメントに対する対応策について弁護士が詳しく解説いたします。
2 カスタマーハラスメントの分類
カスタマーハラスメントと一言で言っても、その態様は様々であり、その行為態様に応じて対応策も様々です。そのため、カスハラをある程度類型化することで対応策のマニュアル化に役立ちます。
カスタマーハラスメントは大別すると以下のように類型化できます。
・時間拘束型
・リピート型
・暴言/脅迫型
・揚げ足取り型
・SNS投稿型
・正当な理由のない過度な要求型
・セクハラ型
・その他
3 カスタマーハラスメントが抵触する法律
カスタマーハラスメントは行為態様、その程度によって、以下の刑法上の犯罪に該当する可能性があります。
【傷害罪】人の侵害を傷害した
【暴行罪】暴行を加えたが、人を傷害するに至らなかった
【脅迫罪】生命、身体、自由、名誉または財産に対し危害を加える旨を告知して人を脅迫すること
【恐喝罪】人を畏怖して財物を交付させること
【強要罪】生命、身体、自由、名誉または財産に対し危害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害すること
【名誉毀損罪】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること
【侮辱罪】公然と人を侮辱すること
【信用毀損及び業務妨害】虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害すること
【威力業務妨害罪】威力を用いて人の業務を妨害すること
【不退去罪】要求を受けたにもかかわらず、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しないこと
その他、軽犯罪法においても、日常生活の道徳規範に反する軽微なものが処罰の対象とされており、カスタマーハラスメントに類する行為が様々な法律・規制に抵触する可能性があります。
4 対応策を講じる必要性
カスタマーハラスメントへの対応策を講じることは、以下の観点から見ると、単なる「顧客対応の一環」にとどまらず、企業経営の安定、業績向上にもつながります。
・離職率の低下
カスタマーハラスメント対応を適切化することにより、従業員の負担軽減を図り、職場環境を改善することができます。
過度なクレームや理不尽な要求に日常的にさらされることは、従業員の精神的ストレスを蓄積させ、うつ病や適応障害などの精神疾患を引き起こすリスクを高めます。これにより離職率が上昇し、職場に対する不安感も蔓延する恐れがあります。
カスタマーハラスメントに対して明確な方針と対応策を定めることで、業務ストレスを軽減するだけでなく、従業員に「会社が守ってくれる」という安心感を提供し、働きやすい環境を整えることが可能で、離職率の低減に資するでしょう。
・非ハラスメント顧客へのサービスの向上
また、こうした対応策により、適切な顧客との関係を維持しつつ、非ハラスメント顧客(通常の顧客)に対してより質の高いサービスを提供する余力が生まれます。理不尽なクレームへの対応に時間や労力を奪われることなく、真に企業の価値を高めるためのサービス向上に集中できる環境づくりが可能になります。
・顧客の選別
さらに、明確な対応基準を設けることにより、企業にとって好ましくない顧客(すなわち、業務妨害や過度な精神的負担を強いる顧客)を自然と遠ざけることができます。結果として、企業文化や従業員の士気を守り、持続可能な経営を実現するための土台を築くことができるのです。
5 カスハラへの事前対策(マニュアル化)を進めるにあたっての注意点
カスタマーハラスメント対策として、対応マニュアルの整備は有効な手段ですが、その制定内容・制定後の運用には一定の注意が必要で、特に以下の2点については細心の注意が必要です。
・従業員による身勝手なカスハラ認定を防止する
従業員が独自の判断で顧客を「カスハラ」と認定し、粗雑な対応をすると、それがSNSなどで広まってしまい企業の社会からの信頼を低下させる原因となります。また、自身の業務を簡略化したいがために、身勝手にカスハラ認定をするという問題従業員がいないとも限りません。
そのように、マニュアルに基づかない恣意的な対応は、真に対応が必要な顧客対応を誤り、企業の評判を損なう結果になりかねません。そのため、マニュアルは恣意的な解釈ができない文言を用いた上で、具体的な事例や基準を示すなどにより、従業員が適切に判断できるよう教育・研修を併せて実施する必要があります。
・世間とのギャップが大きくなりすぎないように注意する
企業がカスタマーハラスメント対策を講じたとしても、その内容や運用方法によっては「顧客の声を軽視している」「企業側に都合の良い主張ではないか」といった世間からの批判にさらされるおそれがあります。対策を講じる際には、社会的理解を得るための透明性や説明責任を確保し、合理的かつ社会通念に照らして妥当な範囲で運用することが求められます。
6 カスハラが実際に起こった際の対応
カスタマーハラスメントが発生した場合、その事実関係の正確な把握が最も重要です。曖昧な記憶や感情的な対応ではなく、客観的な証拠に基づく冷静な対応が求められます。
このような場面においては、社内調査のみならず、必要に応じて弁護士などの第三者的立場の者に事実調査を依頼することが有効です。弁護士による調査は、法的視点に基づいた中立的かつ専門的な事実認定を可能とし、社内では判断が難しいケースにおいても適切な方向性を示すことができます。また、調査結果をもとに、顧客との対応方針や今後の防止策を検討・実施することで、同様のトラブルの再発を防止することにもつながります。
7 まとめ
カスタマーハラスメントは、企業のサービス品質や顧客満足度だけでなく、従業員の心身の健康や職場環境にも重大な影響を及ぼします。だからこそ、企業として明確な対応方針を定め、マニュアル化・研修・法的対応体制の整備を行うことが不可欠です。
弁護士にマニュアル化・研修・法的対応体制の整備について依頼することは適切ではありますが、さらに、顧問契約を結ぶことによって、マニュアル外のインシデントが生じた際に迅速かつ的確な対応を可能とする大きな支えとなります。問題が発生した際にすぐに専門家へ相談できる体制を整えておくことは、従業員の安心感にも直結し、企業のリスク管理の観点からも非常に有効です。
カスタマーハラスメントへの対応策の整備やマニュアルの運用には、「危機管理」の視点が不可欠です。不十分な対応は、従業員の離職や企業イメージの悪化を招きかねません。つまり、カスハラ対策は単なる顧客対応ではなく、企業を守るための重要な危機管理施策なのです。橋下綜合法律事務所では、企業に関する危機管理業務を多数取り扱っており、コンプライアンス研修、危機管理講習会の実施経験もあります。カスタマーハラスメントへの実効的な対応についてお悩み・不安がございましたら一度、弊所にお問い合わせください。
<弁護士 杉山幸太郎>