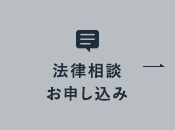2025/09/22 弁護士雑感
労働条件通知書とは?就業規則や雇用契約書との違い~労務管理に必須の3種の書類とは~
1 はじめに
企業経営において、従業員との良好な関係構築と法令遵守は不可欠です。しかし、労務管理に必要な書類は数多く、煩雑でありそれらを正しく理解し、適切に運用することは容易ではありません。もっとも、それら書類は、法令上、作成や従業員への提示を義務付けられている物の他、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、企業の安定的な成長を支えるなど、極めて重要な役割を果たします。
本記事では、労務管理に関わる書類のうち、「労働条件通知書」「雇用契約書」「就業規則」の3つの書類のそれぞれの概要や違い、そして企業が健全な労務管理を行うために必須となるポイントについて解説いたします。
2 労働条件通知書・就業規則・労働契約書の概要
各書類の概要は以下の通りです。
労働契約書:
労働者と使用者との間で個別に締結される契約。労働条件通知書との大きな違いは、労働者と使用者の双方の合意が示されている点。
労働条件通知書:
労働条件を文書で明示するための書類。労働基準法第15条に基づき、提示することが義務付けられている。
就業規則:
会社全体の労働条件や規律などを定めたルール。常時10人以上の労働者を雇用する企業は、作成・届出が義務付けられている(労働基準法第89条)。
3 必須の書類は?
端的に言うと、全ての企業において「労働契約書」は必要ないが、「労働条件通知書の交付」は必要で、さらに、一定以上の規模を有している事業所では、「就業規則」の制定と届け出が必要となります。
労働契約書は、労働者と使用者との間の権利義務を明確にするための重要な書類です。日本の法律では、労働契約を結ぶ際に書面での契約書の作成を義務付けているわけではありませんが(口頭契約も有効)、労働基準法第15条により、「労働条件通知書」によって一定の事項を書面で明示することが義務付けられています。
この通知書は、労働契約書に必要事項を記載して、代替として(兼用して)使われることが多いですが、実務上は労働条件通知書と労働契約書の両方を交付することが望ましいとされています。トラブル防止の観点からも、双方が署名押印した労働契約書を作成しておくことで、後日の証拠となり、紛争を未然に防ぐ効果があります。
従業員が常時10人以上の事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。これには正社員だけでなく、パート・アルバイトも含まれます。違反した場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。
4 労働条件通知書、就業規則との違い
労働契約書と労働条件通知書、就業規則は、それぞれ異なる性質と目的を持っています。
労働契約書と就業規則の間に矛盾が生じた場合、原則として労働者にとって有利な条件が優先されます(労働契約法第12条)。そのため、就業規則と整合性のある内容で労働契約書を作成する必要があります。
スタートアップ企業や、事業規模が小〜中規模の企業においては、手続きの簡便性、迅速性が求められるため、労働契約書と労働条件通知書は一つにまとめるケースが多いでしょう。その場合は、労働条件通知書の要件を充たした書面に労働者、使用者双方の合意の文言と署名押印を備える必要があります。
5 労働条件通知書作成の際の注意点
雇用時には一定の事項を明示する必要があると前述しましたが、その内容が、絶対的明示事項と相対的明示事項と呼ばれるもので、労働条件通知書にはそれらの事項を記載する必要があります。
〇 絶対的明示事項について
これは、労働基準法施行規則第5条により、雇用時に必ず書面で明示しなければならない事項として定められている事項で、雇用時に交付する労働条件通知書に記載しなければなりません。その具体的内容は以下の通りです。
・労働契約の期間
・就業の場所および従事すべき業務内容
・始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇
・賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切および支払時期
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらの事項が明確にされていないと、労働者とのトラブルや法令違反のリスクが高まります。特にスタートアップ企業においては、労務管理の体制が整っていないことも多いため、これらの基本事項は必ず文書化しておくべきです。
〇 相対的明示事項について
一方で、労働基準法施行規則第5条の2では、「相対的明示事項」として、定めがある場合には明示が必要とされる事項があります。以下のような内容が該当します。
・昇給に関する事項
・退職手当の有無および計算・支給方法
・臨時の賃金(賞与など)、最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる費用(制服代、研修費など)
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰・制裁に関する事項
・休職に関する事項
これらは、会社が該当の制度やルールを設けている場合に、労働契約書や労働条件通知書に記載する必要があります。
そして、現代の労働環境に対する世論の変化によると、社内の就業ルールは順次アップデートすることを迫られています。制度を整備していく過程で相対的明示事項に該当するルールが追加されることも多いため、契約更新や見直しの際には適切に反映させることが重要です。
6 まとめ
企業が健全な組織運営を行うためには、労働条件通知書または労働契約書を適切に作成し、法令に則った労務管理を行うことが不可欠です。労働条件通知書や就業規則との関係性を理解し、絶対的・相対的明示事項を正しく反映させた契約書を用意することで、労使間の信頼関係を築き、リスクを最小限に抑えることができます。
弊所では、多数の顧問先から、日々労務管理に関する相談を受けて付けており、各企業の実情に応じて適切な労働条件通知書及び労働契約書、就業規則の作成やその助言を行っております。
それら労務管理に必要な書類の作成や助言は単発のご依頼も承っておりますが、顧問契約を締結した場合、日々の当該企業への法的サポートを通じ、より実情に応じた適切な書類作成・就業規則制定のサポートが可能となります。
労務管理に関してお悩みの場合は、一度、弊所へお問い合わせください。
〈弁護士 杉山幸太郎〉